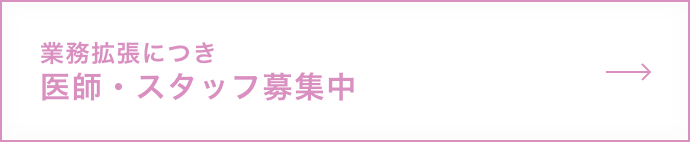初診の方06-6281-9000
再診の方06-6281-3788(初診電話が繋がらない場合はこちらへ)
事務局(患者様以外の方):06-6281-8801
月・火・木・金18時30分まで水・土16時まで祝13時まで
BLOG
ブログ
- トップページ
- ブログ
春木レディースクリニックに
ご相談ください
春木レディースクリニックに ご相談ください
初診の方06-6281-9000
再診の方06-6281-3788
(初診電話が繋がらない場合はこちらへ)
事務局(患者様以外の方):06-6281-8801
月・火・木・金18時30分まで
水・土16時まで
祝 13時まで